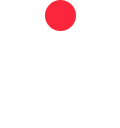-

- 表彰式で女子48キロ級の三宅は贈られた銅メダルを客席に向かって見せる(撮影・松本俊)
人はメダルの色に一喜一憂する。誰だってより輝く方がいいに決まっている。だが、選手は必ずしもそうではない。銅メダルを首にかけた女子重量挙げ48キロ級の三宅宏実が、こんなコメントをした。「前回とは年齢が違うので(メダルの)重みが全然違う。色は銅でも1番うれしい」。彼女には12年ロンドン大会の銀より、今回の銅の方が輝いて見えるのだ。
選手にとってのメダルとは、人生そのものが凝縮された褒美なのだ。そして、障害物の少ない舗装道路を進んで手にした褒美より、山あり谷ありの獣道を歩んでつかみ取った褒美の方が値打ちがある。三宅の4年間がいかに過酷な獣道だったかは、そのコメントから想像できる。腰や膝が痛み、記録は伸びない。極めるための鍛錬と、笛吹けども踊らぬ肉体との折り合いにもがき続けた。今回も腰痛の痛み止めの注射を打っての試技だったと聞く。
20年前、96年アトランタ五輪で同じ光景を見た。女子マラソンで3番目にゴールした有森裕子は、直後のインタビューでこう言った。「メダルの色は銅かもしれませんけれども(中略)初めて自分で自分をほめたいと思います」。私は流行語になったこのフレーズより、あの笑いながら泣いていた顔を忘れることができない。天真らんまんの笑顔で首にかけた92年バルセロナ大会の銀メダルより、ずっと感慨深いメダルだったのだ。
メダルの輝きは人生を保証するものではない。バルセロナの後、有森はそれを思い知る。祝福の熱狂が去ると、孤立していった。実業団での変化のない生活が戻る一方で、「あの人は特別だから」の陰口も聞こえてくる。メダルの先にはバラ色の未来などなかったのだ。目標も、走る意味さえも見いだせず、両足かかとの手術も受けた。もがき続けた4年間。銅メダルは長い苦悩の時間を自らの力で断ち切った証しであり、人生を真に輝かせるための希望だったのだ。
リオ五輪で日本選手団は金14個を目標に掲げている。競技初日、競泳で萩野公介が金メダルを獲得して、上々のスタートを切った。しかし、選手にとってメダルの価値は色だけでははかれない。この日、銅メダルを首にかけた4人の顔も、しっかりと記憶にとどめておきたい。【首藤正徳】