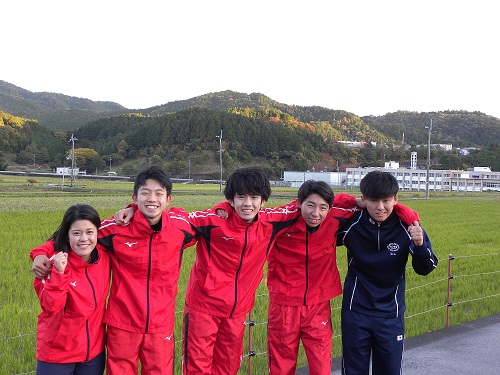午後5時50分。冷えた体育館の床にブルーシートが敷かれ、そこにテーブルが運ばれてきた。用意されたのは半分がチョコレート、半分クリームのホールケーキ。横にはアップルジュース。壁には「慎之介 誕生日おめでとう」と書いた紙が貼られ、慌ただしく誕生日パーティーが始まった。
「慎之介、あと5分しかないで!」
11月9日に16歳の誕生日を迎えたのは、大阪・豊中高校能勢(のせ)分校の卓球部員、沖沢慎之介(1年)。祝福を受けながら照れた表情を見せ、ケーキをほお張ると、小走りで帰っていった。学校近くを走るバスに間に合わなければ、次は1時間後になる。通学に1時間半かかるため、乗り遅れると手痛い。入学から半年、バスの時刻表はすぐに頭に入った。
■大阪最北端、年々先細る町
豊中高校能勢分校。大阪府最北端の豊能郡能勢町にある唯一の高校だ。町の人口は10月末時点で9719人。大阪の中心地「梅田」からは、電車とバスで約1時間半を要する。
分校から北に1・5キロ進むと付属農場があり、1年生は必修科目「農業と環境」で基礎を学ぶ。大根やほうれん草を育て、上級生になれば鶏を飼育。養蜂も行う。「蜂蜜」や「たまご」は地元で好評の逸品だ。
能勢分校は1954年、能勢高校として創立した。だが、1998年に1万5000人を超えていた町の人口は年々減少。過疎化に加えて、少子化も深刻な問題となっている。
能勢高校は定員割れが続き、18年春に分校となった。だが、20年の入試も定員に到達せず、現在の在校生は3学年で約80人にとどまる。地元中学生が他の市町村へ進学する現状に危機感を抱き、立ち上がったのが部員4人の能勢分校卓球部だった。
山本翔斗主将(3年)には、苦い思い出があった。
「僕がいた小学校、中学校は、閉校になってしまいました。『帰る学校があってほしい』『能勢分校を残したい』というのは、自然と思っていました」
町内の教育現場が劇的に変化したのは、4年前の16年春だった。山本が卒業した岐尼(きね)小学校など6校(うち1校は15年に閉校)を能勢小学校の1校に統合。さらに山本が学んでいた能勢西中学校も、2年への進級時に能勢東中学校と統合され、能勢中学校に生まれ変わった。校舎の場所は変わり、校歌もなくなった。その寂しさは身をもって実感していた。
■部員1人、顧問と2人の練習
わずか1年前まで、卓球部は山本1人だった。能勢分校入学後、中学でも打ち込んだ卓球を続けることに決めた。だが、現実は厳しかった。顧問が練習に来られない日は、ボールを打ち合う相手さえ、いなかった。
「やる気がなくなって…。試合もないし、何を目指してやったらいいのか、分かりませんでした」
アルバイト漬けの日々を過ごして1年が過ぎ、赴任してきたのが植木美里監督(30)だった。学生時代はテニス部で、卓球未経験だった体育教師は真正面から向き合ってくれた。
「2年生の5月に試合に出て『やっぱり卓球って楽しいな』と思いました」
植木監督には「練習しても、休んでもいい。全てあなたが決めなさい。練習する時は、とことん付き合う」と告げられ、マイラケットを購入した顧問と、毎晩遅くまでラリーを続けた。「将来は自衛隊になりたい」と口にすると「じゃあ、毎日走ろう」と背中を押された。雨の日も、雪の日も1日6キロ。鹿、イノシシ、時にはタヌキやヘビを横目に、監督と2人で学校の外周を走り続けた。
田んぼ道を走っていると、地域住民が応援してくれた。
「僕、絶対に駅伝部やと思われてました」
そう笑う教え子の姿は、植木監督も突き動かした。
「『この子たちが帰る場所を作りたい』と思うようになりました。うちの体育館は、みんなが集まってくる場なんですよね。卓球部しかいない体育館に来たら、広々としたスペースで、思い切り体を動かせる。卒業生も体育館にやってきます。そういう場所って、必要だと思うんです。うちは就職率も高い。ここが『最後の学校』になるかもしれない。だから『この場所を残したい』と思いました」
■御所実ラグビー部がヒントに
今年もまた、じめじめとした梅雨がやってきた。いつもと違うのは新型コロナウイルスの影響で、久しぶりに顔を合わせた友人がマスクをつけていることだった。20年6月。コロナによる休校が明け、分校に生徒が戻った。
卓球部には19年12月に山本と同学年で軽音楽部だった三宅晋平(3年)が、兼部という形で入部。休校明けには1年生の沖沢が加わった。
当初、自衛隊だった山本の夢はスポーツトレーナーに変わっていた。専門学校の試験が終わった6月下旬、勉強が落ち着くタイミングを見計らっていた植木監督から、ある提案を受けた。
「こんなん、面白そうじゃない?」
全国高校ラグビー大会で4度の準優勝を誇る御所実(奈良)の記事だった。過疎化が進む御所市に全国から高校を招く「御所ラグビーフェスティバル」を毎夏開催。約1週間のイベントを部員が運営し、地域住民も加わって、町が活性化する-。植木監督はそこにヒントを見いだしていた。
「新入生の勧誘はもちろん大事。でも、この学校の場合、それだけでは根本的な解決にならないと思う」
山本の目は輝いていた。
「『楽しそうやん!』って思いました。すぐに『やろう!』ってなりました」
もう1人の3年生、三宅も出身の小中学校が学校統合でなくなっていた。
「『面白そうやな』って思いました。卓球部っていう居場所がずっとあってほしい。卒業して、前を通った時に学校がないのはさびしい。みんなが帰ってくる場を守りたかったです」
■手作り大会「翔晋杯」の開催
11月7日に能勢分校で手作りのイベントを開催すると決めた。大会名は「翔晋杯」。3年生2人の名前から1文字ずつを取った。
準備は早速始まった。山本がかねて卓球の指導を受けてきたコーチの縁で、卓球用品メーカーの「VICTAS」に熱意を伝えた。その思いに共感した同社は16年の全日本選手権女子ダブルスで優勝を飾った天野優さん(28)に声をかけ、無償での参加が決まった。
山本、三宅を中心に地元中学校には「参加、お願いします」と電話で要請。2台しかなかった卓球台は10台必要で、能勢町や教育委員会にもイベントの説明に出向いた。廃校となっていた小学校に眠る卓球台など、地元住民らの協力もあり、6台の寄贈を受けた。最後は2台をレンタルし、大会前日の夜遅くまで準備は続いた。
迎えた当日。能勢町や近隣の中学校6校から、約40人が集まった。新型コロナウイルスの状況も勘案し、想定した通りの参加人数だった。中学生は天野さんの講習会に目を輝かせ、団体戦で盛り上がった。普段は静かな体育館が、活気に満ちあふれた場所になった。
能勢分校の卓球部員は4人に増えていた。「翔晋杯」の約2週間前、淀谷麟太郎(2年)は植木監督に「卓球やれへん?」と声をかけられた。「運動するのは好き。でも『自分が楽しければいいや』っていう性格です」と笑い、こう明かした。
「先生と『翔晋杯を手伝う』って約束をしたんです。本音は『どうでもいい』と思います。でも、約束は守ろうと思いました」
駐車場係、アナウンス、表彰式…。分校の部員4人は、豊中高校卓球部4人、友人1人の助けを借りながら、中学生が分校での1日を楽しむために奔走した。
「楽しかったです!」
「来年もやってください!」
夕方、中学生の声を聞いた1年生の沖沢が言った。
「『これは期待に応えないと』って思いました。今年は3年生の先輩2人が、自分にとって難しいことを全部やってくれました。正直、最初に聞いた時は『卓球部だけでこんなんやれるの?』と思いました。今度は僕たちがこれを続けて、入学者を増やしたいです」
「先生との約束」を果たした2年生の淀谷は、違う意味で刺激を受けていた。
「自分より年下で自分より強い人を見たら、なんか頑張ろうって思いました」
副将として山本を支えた3年生の三宅は、少し照れくさそうに明かした。
「僕、中学生の頃は教室の隅っこに座っている子でした」
能勢分校で軽音楽部に入部し、人前に立てるようになった。兼部の形で1年前に入った卓球部では「人前に出ることが楽しいと思えた」と自信を得た。元々は専門学校志望だったが、大学の外国語学部を目指す。
「最近の目標は『翔晋杯を成功させたい』でした。今の目標は希望の大学に進んで通訳になることです」
■学校のカリキュラムにない勉強
体育館横の体育教官室には「翔晋杯」参加者のアンケートが並べられていた。能勢分校を知らなかった中学生が記した「興味を持った」の文字に、部員1人の時代から歩んできた山本の胸中は自然と熱くなった。
「課題を見つけて、どう解決するかの道筋を学びました。社会に出て、壁にぶち当たって『ダメや』って思った時に、どうするのか…。学校のカリキュラムにはない勉強ができました」
大切な3年間を部活動にささげた。「やって良かったと思います」と胸を張る。
「卓球部で人と人とのコミュニケーションの大切さ、継続して1つのことを頑張ることの大切さも学びました。あとはやっぱり…」
そうほほえんで続けた。
「この学校のことをもっと知ってもらって、たくさんの中学生に入ってきてほしいです」
卒業式の日まで、山本は大好きな体育館で卓球を続ける。その場所こそが、宝物だ。【松本航】